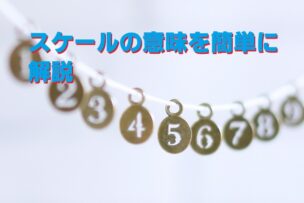
音楽用語でスケールという理由
音の並び方に名前をつけたもの
1オクターブに決まった目盛り(スケール)を付けてまとまり感をだす
1オクターブに散らばる音のポジション名である音階の事を音楽用語では音を目盛りの様に使う事からスケールと呼びます。
そしてドレミファソラシ7つの音階(スケール)の事を「ダイアトニックスケール」と呼び
現代音楽で我々が演奏したり歌ったりする時はメロディの自然さがしっくり来るので無意識にその枠からはみ出さない様に使っています。
音階の物差しの目盛りは並び方が決まっている
ダイアトニックスケール、いわゆるドレミファソラシドは決まった法則で並んでいます
小学校の音楽の時間で習ったと思いますが、ただ1音ずつ上昇していき、1オクターブで一周するのではなく、間に半音が挟まれています。
その半音の位置は2か所。
ミとファの間とシとドの間で、なぜそのような並びになるのかは、音の周波数の倍数を使うことによって科学的に解明されていて
一番心地よく聞こえる場所に半音が収まるように自然にスケールが出来ているのです
ドレミがCやDなどとは違う理由
基本のスケールに絶対音である音名をアルファベットでつけてあります
絶対音ですからAという音名の音の高さは例えば440ヘルツと決まれば、どのスケールで使われようと440ヘルツの音はAであるという国際的な基準があります
ところが、ドレミが移動するという理論があり、ライトミュージック(jazzやポップスなどの軽音楽)を演奏、作曲するのに非常に理に適った理論なので、こちらを採用することが多くなっています
大昔は音名の一つひとつにニックネームのような名前が付いていましたが
歌を伝承しやすいように音名にアルファベットを割り当てることになり、ラの音から始まるラシドレミファソラと歌うマイナースケールを基準に主音となるラの音からアルファベット順にイタリア語のラシドレミファソラに英語、ドイツ語のA B C D E F G Aの7つの音名を付けたと言われています
その後、ドレミファソラシドを使ったメジャースケールが主流となったため、そのままC D E F G A B Cの英語名とドレミファソラシドのイタリア名の並びが同じになりました
つまり、ミとファの間=EとFの間、シとドの間=BとCの間がそれぞれ半音で一致するわけです
どちらも最初は音名でしたが、ドレミの方を音階としてミとファの間シとドの間が半音の並びのスケール上の音を表す時に使用する理論が出てきました
スケールのドがCの絶対音と同じCの長調(メジャー)なら半音の位置も同じです
C D EF G A BC
ド レ ミファ ソ ラ シド
ドレミ~をC D E~と歌っても何の問題もありません
ドレミという物差し(スケール)を移動させるという考え方
ところが、調が変わってDの長調=Dメジャーになると、音階が
D EF G A BC Dのままでは
ド レ ミファ ソ ラ シドのスケールの目盛りに合わないため曲になりません
この場合Fに♯をつけて半音上げ、Cにも♯をつけて半音上げることでド レ ミファ ソ ラ シドの目盛りと半音間隔の位置が一致します
D E F♯G A B C♯D
ド レ ミファ ソ ラ シド
この場合Dメジャーの歌を声に出してD E F♯G A B C♯Dと歌うよりは
Dのドレミファソラシドと歌った方が歌いやすいだけでなく調性(何の音が主音かといった音の並びの感覚)が解りやすいのです
移動ド 固定ド どちらも正しい
このドレミが移動する、移動ドという考え方は便利な考え方ですのでこのブログではこの理論を採用しています
反対に音楽教室を土台にしているピアニストはじめクラシック系の多くの人は調が変わってもレミファ♯ソラシド♯レ~と歌う、固定ドの考え方です
つまりFの長調で童謡チューリップを歌うと、移動ドの人はキーFであっても主音Fをドと歌うので「ドレミードレミー」と歌うのに対して
固定ドの人は主音のFをファと歌うので「ファソラーファソラー」と歌うのです
私は歌いにくい上にドレミのフィーリングがブレてしまいやすいので余り好きではありません
しかし、昔から根強く残っている音楽教育の基本の理論ですので根強く残っていて避けては通れません。
プレイヤー同士打合せ、会話をする時は相手が固定ドで話しているのか、移動ドで話しているのか見極めて話さないと話が食い違ってしまいますので注意が必要です
コード=和音の意味は簡単
音を一つ飛びに重ねて和音が完成
最も使われるダイアトニックスケール上のコード
五線譜の上の音を一つ飛ばしに重ねると和音=コードになります
詳しくは別の記事で書いていますので更に詳しく知りたい場合は参考にしてみてください
ダイアトニックスケール上のそれぞれの音の上に一つ飛ばしの音を重ねて構成される和音をダイアトニックコードと言い
スケール上の音をそのまま使っているので決められた調の中では安定して最も多く使用されます
ドミソの和音を主和音とし、Ⅰ(イチ)の和音と呼びます
そのほかのダイアトニックコードの種類は以下の通り
スケール上の音にただ一つ飛ばしで音を3つ重ねるだけです
Ⅰ(イチ)ドミソ
Ⅱ(ニ) レファラ
Ⅲ(サン)ミソシ
Ⅳ(ヨン)ファラド
Ⅴ(ゴ) ソシレ
Ⅵ(ロク)ラドミ
Ⅶ(ナナ)シレファ
キー(調)が♯や♭の調号がなにも付かないCの場合
ドレミファソラシドのダイアトニックスケール上の
ダイアトニックコードのコードネームは
ⅠC(呼び方CメジャーあるいはC)
ⅡDm(Dマイナー)
ⅢEm
ⅣF
ⅤG
ⅥAm
ⅦBm♭5(dim)(Bマイナーフラットファイブまたはディミニッシュ)
キーがFの場合
Fから始まるドレミファソラシドのダイアトニックスケール上に
出来るダイアトニックコードは
ⅠF
ⅡGm
ⅢAm
ⅣB♭
ⅤC
ⅥDm
ⅦEm♭5(dim)
キーがAの場合
Aのダイアトニックコード
ⅠA
ⅡBm
ⅢC♯m
ⅣD
ⅤE
ⅥF♯m
ⅦG♯m♭5(dim)
法則を覚えると簡単になる
ここまで見てくるとスケールから外れないコード(ダイアトニックコード)には
法則があることが分かりますね。
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴのコードはメジャーコード
そのほかはマイナーコード(Ⅶだけは5度がマイナーコードの構成より半音低いのでディミニッシュと呼ぶ)
キー(調)が変わっても法則は変わりません
ちなみにマイナーキー(短調)は
ラシドレミファソラと歌うダイアトニックスケールです。
歌ってみるとメジャーキー(長調)と比べて暗い感じがします
上の表記に戻ってみると
ドがCならラはAとなり
ⅥAm(ここがマイナーキーの主音)
ⅦBdim
ⅠC
ⅡDm
ⅢEm
ⅣF
ⅤG
と並べ替えて理解します
あるメジャーキーは別のマイナーキーと同じ
AマイナーキーはCメジャーキーの同種短調と言い
スケールとコードの構成は
Cメジャーキー=Aマイナーキーとなります
後はⅠ(ドミソ)の和音中心の曲か
Ⅵ(ラドミ)の和音中心の曲かで
CメジャーなのかAマイナーなのか調が決まります。
同じくドがFならラはDとなり
ⅥDm(ここがマイナーキーの主音)
ⅦEdim
ⅠF
ⅡGm
ⅢAm
ⅣB♭
ⅤC
と並べ替えて
DマイナーキーはFメジャーのキーの同種短調と言い
スケールとコードの構成は
Fメジャーキー=Dマイナーキーとなります
マイナーキーの曲自体が「マイナー」という位なので
メジャーキーほど多くありません。
音楽理論的には短調(マイナーキー)はもう少し解説が必要ですが
ポップス系の曲の大半はメジャーキーなので
今はひとまずこの理解の仕方でよいでしょう。
基本はメジャーキー
メジャーとマイナーの差にはまだまだ
格差が隠れています
ダイアトニックコードのⅠ、Ⅳ、Ⅴのコードがメジャーコードですね。
スケール上の音を使ってコードを作ると自然とこうなるわけですが
単なる偶然ではありません
Ⅰのコード構成音ドミソ
Ⅳのコード構成音ファラド
Ⅴのコード構成音ソシレ
この3つのコードの構成音だけでダイアトニックスケールの全ての音を網羅しています。
これはメロディにコードをつける時に
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴのコードさえあればどのメロディにも対応できることを意味しています。
この3つのコードを主要3和音(スリーコード)と呼び
他のコードとは別格の扱いをされています。
まさにメジャーの中のレギュラーメンバー、スターティングメンバーと言えます
機能的にもこのⅠ、Ⅳ、Ⅴの3つのコードには重要な役割が与えられているのです
音感を鍛えるにはまずこの3つのコードを感じる事が先決です。
音感の身に付け方については別の記事で詳しく書いています
まとめ
スケールとは音の並び方に名前をつけたもので1オクターブに決まった目盛り(スケール)を付けてまとまり感を出している
軽音楽はドレミという物差し(スケール)を移動させる移動ドという考え方が便利
音を一つ飛ばしで重ねたものが和音=コード
ダイアトニックスケールの上にコードを構成したダイアトニックコードのパターンは決まっているので覚えやすい
それでは今日はこの辺で。
あなたの音楽ライフが日々レベルアップしていく事を
願っています。



